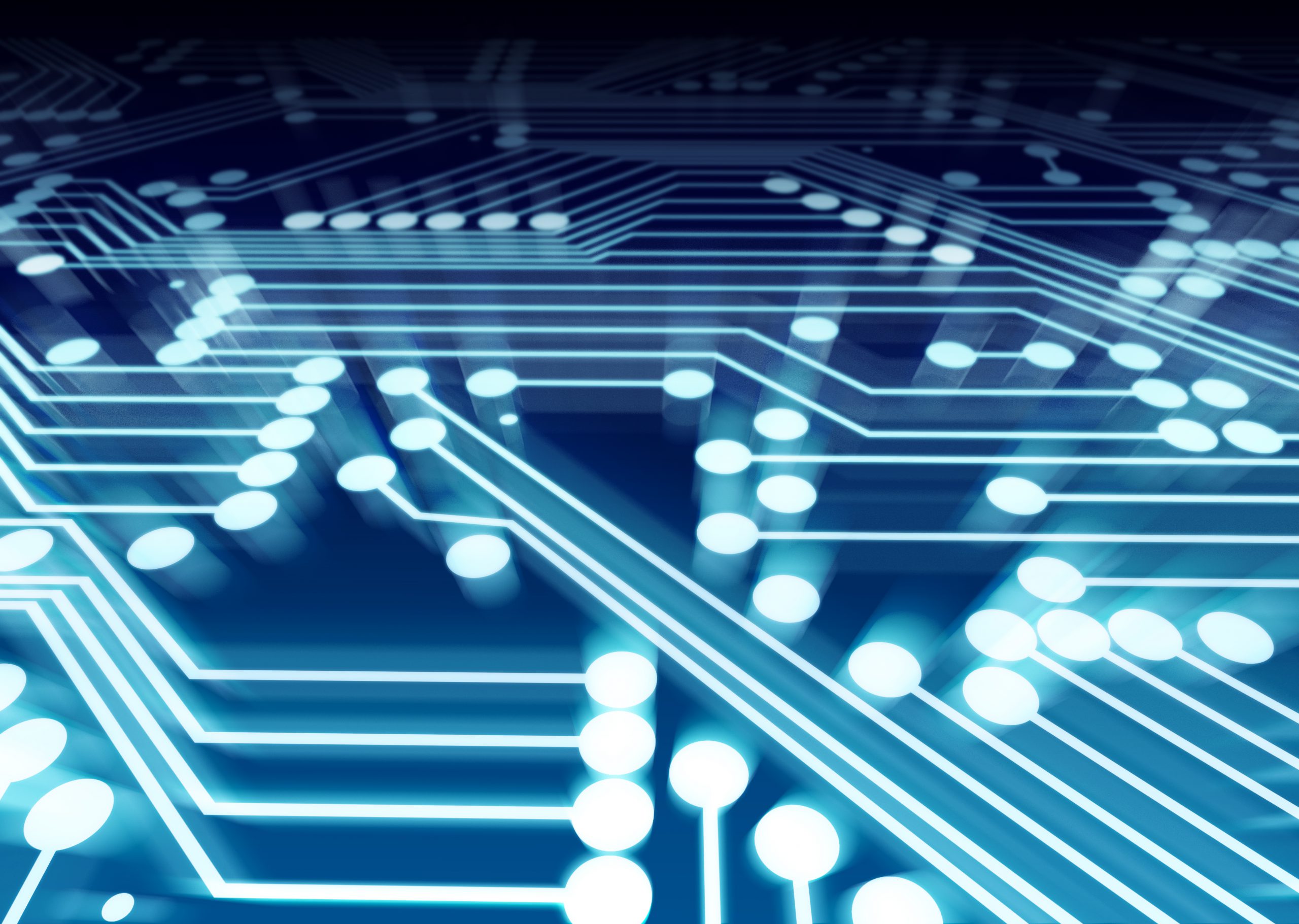「この業務の過程で生じた知的財産権は、私たちに帰属するようになっていますか?」
「仮に相手企業に帰属するとしても、将来的に私達が利用できるようになっているでしょうか?」
弁護士として、企業の法務担当者や経営者の方から、契約書の内容確認を依頼される際に、高い頻度で聞かれるものとして、上記のような質問が挙げられます。
対象となる業務から、著作権や特許権などの知的財産権が生じる可能性がある場合、その業務を委託する側と受託する側のいずれもが考慮すべき事項が、「知的財産権の取り扱い」です。
本記事では、知的財産をめぐる契約書の条項について、実務上よく見る条項例を挙げながら、確認すべきポイントなどを解説いたします。
なお、本サイトを運営する渡瀬・國松法律事務所に知的財産関係に関するご確認を含め契約書の作成やチェックを依頼される場合には、こちらのページからご連絡ください。お見積りは無料ですので、お気軽にご相談ください。
契約書と知的財産権の帰属を定めた条項
知的財産権に関する条項は、大きく分類すると、次の2つに分けられます。
- 知的財産権の帰属について定めた規定
- 知的財産権の利用について定めた規定
この「2つに分けられる」という点は、意外に重要です。取引先企業との力関係を考慮して「そちら側に権利を帰属させるけれど、こちらとしても自由に利用できるようにはさせて欲しい」といった形や「そちら側も、自由に利用して良いので、権利の帰属先はこちらにしてもらいたい。」といった形で交渉することも考えられます。
まずは、「知的財産権の帰属」について定める規定について、みていきます。
知的財産権の帰属に関する規定A:一方当事者全面的帰属型
一番単純な規定は、次のような条項になると考えます。
成果物に含まれる知的財産権(知的財産権を受ける権利を含む。また、著作権については、著作権法第27条および同法第28条に定める権利を含む。以下、本契約において同じ。)および本契約に基づく業務遂行の過程で生じる知的財産権は発生と同時に甲に帰属するものとする。
これは、業務委託契約において良く見られるシンプルな規定で、委託した業務から生じた知的財産権について、一方当事者に全面的に帰属する形で定めた条項になります。
この条項例で実は重要なポイントが、「著作権法第27条及び同法第28条に定める権利を含む。」という点です。
こちらの文言が抜けており、単に「知的財産権は発生と同時に甲に帰属する」となっていると、著作権法第27条と第28条で定められている権利は当然には甲に帰属することにはならないため、注意が必要です(著作権法第61条第2項)。
知的財産権の帰属に関する規定B:部分留保型
一方当事者に知的財産権が全面的に帰属することになると、他方当事者には次のような不都合が生じるリスクがあります。
- 従来から保有していた知的財産権を成果物に組み込んでしまったために、それが相手に帰属することになってしまった…
- 受託した業務とは別の業務にも使える可能性の高い汎用的なプログラムを作ったのに、それも相手に帰属することになってしまい、今後の業務に活かせない…
これらのリスクを回避できる規定として、次のような条項例を見ることがあります。
成果物に含まれる知的財産権(知的財産権を受ける権利を含む。また、著作権については、著作権法第27条および同法第28条に定める権利を含む。以下、本契約において同じ。)および本契約に基づく業務遂行の過程で生じる知的財産権は発生と同時に甲に帰属するものとする。但し、本契約の締結以前から乙又は第三者が保有していた知的財産権および汎用的な利用が可能な発明等にかかる知的財産権は、この限りでない。
この条項例は、経済産業省および情報処理推進機構が公開している「情報システム・モデル取引・契約書」を参考にした条項例であると考えます。
この但書によって、契約の締結以前から保有されていた知的財産権や汎用的な利用が可能な発明等にかかる知的財産権については、契約に基づいて甲に帰属することになるのを阻止することができると考えられます。
知的財産権の帰属に関する規定C:部分留保型
上記の一方当事者全面的帰属型と部分留保型のいずれも、基本的には一方当事者に権利を集中させようとするものです。
これに対し、権利を分散させ、両当事者の共有にしようとする次のような条項例も存在します。
成果物に含まれる知的財産権(知的財産権を受ける権利を含む。また、著作権については、著作権法第27条および同法第28条に定める権利を含む。以下、本契約において同じ。)および本契約に基づく業務遂行の過程で生じる知的財産権は、甲および乙の共有とする。
業務提携契約や共同研究開発契約だと、このように権利を分散させる形が採用されやすい印象です。
もっとも、特許権や著作権などの知的財産権を両当事者の共有とする場合には、特に次の点に注意する必要があります。
1点目として、特許を受ける権利が両当事者の共有となった場合、各当事者は、他の当事者と共同でなければ、特許出願することができません(特許法第38条)。
2点目として、特許権が両当事者の共有となる場合、各当事者は、自分自身で特許権の全部を実施することはできるものの、第三者に対して自己の持分を譲渡し、あるいは自己の持分について質権を設定するためには他の当事者の同意を得なければなりません(特許法第73条)。
3点目として、著作権が両当事者の共有となる場合、各当事者は、他の当事者の同意を得なければ、著作権を行使すること(第三者に対して利用許諾することのみならず、自分自身で利用することも含みます。)ができません(著作権法第65条)。
4点目として、著作権が両当事者の共有となる場合、各当事者は、第三者に対して自己の持分を譲渡し、あるいは自己の持分について質権を設定するためには他の当事者の同意を得なければなりません(著作権法第65条)。
特に3点目の「相手方当事者の同意を得なければ、自分自身で著作物を利用することもできない」という制約は厳しいため、著作権を共有とする場合には、この点を慎重に検討する必要があると思います(少なくとも契約において、各当事者が自由に著作物を利用できる旨を定めておく方が良いと思います。)。
なお、共有型の派生形として、次のような規定を見ることもあります。
本契約に基づく業務遂行の過程で生じる知的財産権(知的財産権を受ける権利を含む。また、著作権については、著作権法第27条および同法第28条に定める権利を含む。以下、本契約において同じ。)は、当該知的財産権を生じさせた各当事者に帰属する。但し、両当事者が共同で生じさせた知的財産権については、甲および乙の共有とする。
契約書と知的財産権の利用を定めた条項
知的財産権の帰属について、上記の一方当事者全面的帰属型、部分留保型、共有型のいずれを採用したとしても、次に問題になるのが「知的財産権の利用に関する定め」になります。
一方当事者全面的帰属型であれば、知的財産権が帰属しなかった当事者が、どのように知的財産権を利用できるのかを定める必要があります。
部分留保型であれば、一方当事者に留保された知的財産権や一方当事者に帰属することになった知的財産権について、他方当事者がどのように利用できるのかを定める必要があります。
共有型であれば、共有となった知的財産権について、各当事者がどのように利用できるのかを定める必要があります。
「知的財産権の利用に関する定め」においては、次の2点が重要です。
- どういった目的で権利を利用できるのか?
- どういった態様で権利を利用できるのか?
この2点を意識しつつ、具体的な規定ぶりを考える必要があります。
著作者人格権の不行使
知的財産権の帰属について、一方当事者全面的帰属型を採用し、自己に知的財産権の全てを帰属させたとしても、それだけでは、自由に当該知的財産権を利用できない可能性が残ります。
なぜなら、著作権には「著作者人格権」と呼ばれる権利があり、この権利は「譲渡することはできない」とされているからです(著作権法第59条)。
この著作者人格権が行使されると、自由に知的財産権を利用できなくなるため、契約上は、次のような条項を定めておくことが多いです。
乙は、甲に著作権が帰属することになった著作物について、自己に著作者人格権が帰属する場合、当該著作者人格権を行使しないものとする。
下請法と知的財産権
契約において、知的財産権の取り扱いについて、どのように定めるかは基本的に当事者の自由に委ねられています。
したがって、基本的には、契約の当事者の合意により、上記のような条項例のいずれをも採用することが許されます。
しかし、「下請代金支払遅延等防止法」との関係で、親事業者として同法の適用を受ける場合には、次の点に注意する必要があります。
それは、同法について公正取引委員会が公開している「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」において、以下のような記載があることです。
情報成果物等の作成に関し,下請事業者の知的財産権が発生する場合において,親事業者が,委託した情報成果物等に加えて,無償で,作成の目的たる使用の範囲を超えて当該知的財産権を親事業者に譲渡・許諾させることは,法第4条第2項第3号に該当する。
下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準第4-7-(4)
この運用基準との関係で、委託した業務から生じる知的財産権のうち、成果物に含まれるもの以外の知的財産権を自己(=親事業者)に帰属させることはできないことになると考えられる点、ご注意ください。
業務委託、業務提携と知的財産権
知的財産権の取り扱いに関する条項について、少なくとも自己が生み出した知的財産権については、自己に帰属する形とすることを希望されるのが通常と考えます。
しかし、実務上、特に大企業から業務を受託する形になる場合には、大企業の側で「業務委託契約なら、委託者に知的財産権が帰属することになるのが自然である。それ以外の取り扱いは認められない。」といった考えを有していることがあります。
その結果、業務委託契約の形で契約を締結しようとすると、受託者として自己に知的財産権を帰属させることを希望しても、それを実現できなくなってしまうことが多いように思います。
このような場合には、業務委託契約ではなく、業務提携契約の形で契約を締結するように持ちかけることが解決策となることがあります。
実質的には契約の目的が変わらないにもかかわらず、契約の体裁が変わるだけで、知的財産権に関する取り扱いを変えるというのは違和感がありますが、実務上は使えるテクニックかもしれません。
知的財産権をめぐる条項と印紙税法
少し蛇足になりますが、知的財産権をめぐる条項と印紙税の関係についても記載しておこうと思います。
印紙税法において、知的財産権が関係する文書で、課税文書とされているのは、「無体財産権…の譲渡に関する契約書」になります。この「無体財産権」が「特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権をいう」とされています(印紙税法における印紙税額一覧表の第1号文書)。
したがって、契約の知的財産権をめぐる条項の内容として、知的財産権を生み出した当事者から、他方の当事者に対して知的財産権が移転することとなっている場合には、当該契約は第1号文書に該当する可能性があります。
この点については、次の記事が、とても深く検討されているので、こちらをご参照いただくのが良いと思います。
また、印紙税については、税理士の方にもご確認ください。
クラウドサインなどの電子契約を用いた場合に印紙税が生じないと考えられる点については、次の記事の中に詳しく記載しましたので、こちらもご参照ください。
最後に
本記事では、実務上重要な知的財産権をめぐる条項について、条項例を示すと共に、確認すべきポイントなどを記載してきました。契約書の作成や、契約書の確認作業において、本記事が皆様のお役に立てることを願っています。
なお、本サイトを運営する渡瀬・國松法律事務所に知的財産関係に関するご確認を含め契約書の作成やチェックを依頼される場合には、こちらのページからご連絡ください。お見積りは無料ですので、お気軽にご相談ください。